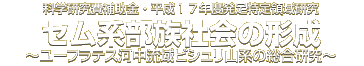|
|
 |
 |
 |
| �u�����j���ɂ�����Z���̌n���A�A�����l�A�r�V�����R�n�v�@ |
�R�c�d�Y�i�}�g��w��w�@�l���Љ�Ȋw�����ȁj |
 |
�@
�u�Z���n�����Љ�̌`���F���[�t���e�X�͒�����r�V�����R�n�̑��������v�Ƃ�������̈挤���Ɏ��g�ނɂ�����A�����w�̗��ꂩ��L�[���[�h�ɂ��Ă̊�b�I�f�[�^������̂��{�e�̖ړI�ł���B���ɁA�Z���n�V�q���Ƃ��̌����Ƃ����r�V�����R�ɂ��Ă̌Ñ㐼�A�W�A�̕����j���̃f�[�^���A�O3��N�I����O2��N�I�O���𒆐S�ɐ����������B
�@�u�Z���v�Ƃ͖{���A��^�����c���Đ��A�W�A�����̑c�ƂȂ����m�A�̒��q�Ƃ��ċ����n���L�ɓo�ꂷ��l���i�w�u���C��ŃV�F���j�ł���B�n���L�ɂ��A�_�͓V�n�n���̎d�グ�Ƃ��Ď���n�������l�Ԃ̍s�����������Ƃ�Q���A�^���𑗂��Ă��ׂĂ̐�������łڂ����ƌ��ӂ����B�������A�_�ɒ����ł������m�A�ɂ͔��M����点�ꑰ�ƂƂ��ɍ^�����c�邱�Ƃ𖽂����Ƃ����B�m�A�ƂƂ��ɔ��M�ɏ�萶���c����3�l�̑��q�̖��́A�Z���A�n���A���t�F�g�ł������B��ʂɁu�����\�v�Ƃ���n���L10�͂́A3�l�̑��q��������ʂ�o���q�������̖��Ƃ��Đ��A�W�A�Ƃ��̎��ӂ̖������A�������A�n���Ɍ��y���āA�e�n�̏����̓m�A����ʂ�o�������W�c�ł���Ɛ�������B
�@���t�F�g�̎q���́A�G�[�Q�C�A�A�i�g���A�A�C�����̃C���h�E���[���b�p��n�𒆐S�Ƃ��鏔���ł���B�n���̎q���́A�G�W�v�g�Ƃ��̎��Ӑ��E�̏����B�����ăZ���̎q���́A���\�|�^�~�A�E�V���A�̏����ł���C�X���G���̑c�ƂȂ�G�x�����܂ށB�u�����\�v�́A�O2��N�I�㔼����O1��N�I�O���̎�v�ȍ��Ɩ��E�������Ȃ�тɒn�����܂�ł���B�n���I�E�����I���т����d������Ă���A�K����������I�ώ����ɂ���Ă܂Ƃ߂��Ă���킯�ł͂Ȃ��B�Z���Ɋւ��Ă����A�����̃Z���̎q���ɐ������鏔���ɂ́A�A�V�����A�A�����̂悤�Ɍ���I�ɖ��炩�ɃZ����n�i��q�j�ɑ�������̂̑��ɃG�����n�A�A�i�g���A�n�A�t���n�Ȃǂ̔�Z����n�̏������܂܂�Ă���B���̈���ŁA����I�ɃZ���n�ł���͂��̃J�i���̓n���̎q���ɐ������Ă���B�u�Z���l�v�ɂ��Ă̌��݂̎����E���T�ɂ݂��ʓI��`�́A�u���݂ɂ����Ă͎�Ƀ��_���l�ƃA���u�l�ɂ���āA�܂��Ñ�ɂ����ẮA����Ƀo�r���j�A�l�A�A�b�V���A�l�A�A�����l�A�J�i���l�A�t�F�j�L�A�l���ɂ���đ�\����鐼��A�W�A�̐l�X�v�Ƃ������̂ł���B�����Z���l�̘b��������́A�A�t���E�A�W�A�n����Ƃ����匾��O���[�v�̂Ȃ��ōő�̃T�u�E�O���[�v�ł��鉏�ʌ���W�c���`�����u�Z����v�Ƒ��̂����B�Z���n����́A�����̋��ʂ��錾��w�I������L����B
3�q�������Ƃ���Ɠ��̌�`�������A��{��b�����ʂł��邱�ƁB�����������E����������Ȃ�e���X�E�A�X�y�N�g�E�V�X�e����L���A�ړ����A�ڔ������Ƃ��Ȃ��Đl�̂Ɛ��ɂ���ē����I�Ȋ��p�����邱�ƁA�Ȃǂł���B�A�b�J�h��A�A������A�A������A�t�F�j�L�A��A�w�u����A�A���r�A��A�G�`�I�s�A����Ȃǂɋ��ʂ��Č����邱����������w�I�����́A�����̌���̘b�҂����̊Ԃɑ��݂������炩�̗��j�I�E�����I�W������������̂ƍl������B
�@�u�Z���v�Ƃ�����́A���ɉ��Ăɂ����āA�[���b�p�n�̎�v�ȃ}�C�m���e�B�[�E�O���[�v�ƂȂ������_���l���w���Ă����Ηp����ꂽ�B�������������ς烆�_���l���Ӗ����鋷�`�́u�Z���v�̗p�@�́A���\�|�^�~�A�E�V���A�̃Z���n���������I�Ɏ����u�Z���v�̖{���̍L����`����藣����āA�����_����`���Ӗ�����u�A���e�B�E�Z�~�e�B�Y���v�̂悤�Ȍ��㐭����̗p��Ƃ��čĉ��H����A���[���b�p�ƒ����̖�������_����ۂɕp�ɂɗp�����Ă���B���̈���ŁA�u�Z���v�̓Z���n����Ƃ������j�I���̂ɂ���ė��t����ꂽ��I�Ȍ���w�I�E���j�w�I�T�O�Ƃ��āA�Ñ㐼�A�W�A�����ɂ����ėp�������Ȃ̂ł���B�Ⴆ�A�W���I�ȃA���u�j�Ƃ��đ����̓ǎ҂Ă���P.
K. �q�b�e�B�̃A���u�j�iHitti 1937�j�̑�P�͂̃^�C�g���́A�u�Z���l�Ƃ��ẴA���u�l�F�Z���n�����̌̒n�Ƃ��ẴA���r�A�iThe
Arabs as Semites: Arabia the Cradle of
the Semitic Race�j�v�ł���B�q�b�e�B�̓Z���l�͌̒n�A���r�A��������e�n�֊g�U���Ă������Ƃ����������̗p���������ŁA�Z���l�̖����I�������́A�C�ƍ����ɂ���Ď��͂���n���I�Ɋu�₵���A���r�A�����̃A���u�l�ɓ��ɂ悭�ۂ��ꂽ�ƍl���Ă���B��q����悤�ɁA�O3��N�I����O2��N�I�ɂ����Ẵf�[�^�������������i�W���Ă��������ł́A�������������͍ו��ɂ����Č������𔗂�����̂ł��낤���A�����I�w�p���̂Ȃ��Łu�Z���v�����ɃA���u�l�ƌ��ѕt�����Ă����Ƃ��ċ����Ă��������B
| �O3��N�I�O���̃Z���n�����ɂ��Ă̕����j�� |
�@����w�I��ɂ�錻�s�́u�Z���n�v�̒�`�ɏ]���A�Ñ㐼�A�W�A�ɂ����ăZ���n�Z���̌n�������ǂ邱�Ƃ́A���������ɂ����ăZ����̎g�p��ǐՂ��邱�Ƃɂقړ������B���������ɂ���ă��\�|�^�~�A�Řb����Ă������Ƃ��ǐՂł���ŌÂ̌���̓V��������ł���A���̎g�p�͒x���Ƃ��O2800�N���ɑk�邱�Ƃ��ł���B�ŌÂ̕����Ƃ����E���N��IVa�w�̌Ðٕ������V�������������킷���̂ł���A����ɑO3200�N���܂ł����̂ڂ�B�Ƃ�����A���łɑO3��N�I�O���̃��\�|�^�~�A�ɂ����āA�V��������ƕ���ŃA�b�J�h��𒆐S�Ƃ���Z������܂��g�p����Ă������Ƃ͊m���ł���B�Ⴆ�A������������I���i�O2900-2750�N�j�ɑ�������Ƃ����V�����������\�ɂ����č^����ŏ��ɉ������������s�s�L�V���̉������̖��Ƃ��ăV��������l���ƕ���ŃA�b�J�h�ꂠ�邢�͂���ɋ߂��Z���n����̐l�����܂܂�Ă���BPala-kinatim�i�u���������̂̎����v�̈Ӂj�AKalibum�i�u���v�j�AZuqaqip�i�u�T�\���v�j�ATizkar�i�u�i�_���j�L������v�j�Ȃǂł���B�O2600�N���̃e���E�A�u�E�T���r�[�t�o�y�̃V�������ꕶ���̏��L���ɂ������̃Z����̐l�����܂܂�Ă���B�܂��������̃t�@�������i�O2600�N���j�Ɋ܂܂��_�v�̃��X�g�ɂ́AE2-su13-ag2
�Ƃ����V��������l���ɑ�����mar-tu�ƋL����A���̐l�����V���������mar-tu�ƌĂꂽ�Z���n�A�����l�i��q�j�ł��邱�Ƃ��L�^����Ă���B���������A�b�J�h��������i�O2334-2154�N�j�ȑO�̃A�b�J�h�ꂠ�邢�͂���ɋߎ�����ÃZ������g�p�����l�X�̍��Ղ́A���\�|�^�~�A�암�Ɍ��肳�ꂸ�A1970�N�ォ��̃G�u���A�e���E�x�C�_���A�}���̞��`���������̌����ɂ��A����ɖk�V���A�A���[�t���e�X�쒆����A�n�u����㗬��ł��m�F�����悤�ɂȂ����B�����ăA�b�J�h��������ȍ~�A���\�|�^�~�A�ƃV���A�ɂ����āA�A�b�J�h���A������Ȃǂ̃Z����̒n�ʂ͗h�邪�ʂ��̂ɂȂ��Ă����B
�@�Ñ㐼�A�W�A�̕����j���Ɋm�F�����ŌẪZ���n�V�q�W�c�Ƃ��Ē��ڂ���Ă����l�X���A�����l�ł���B�ނ�̓V��������Ń}���g�D�imar-tu�j�A�A�b�J�h��ŃA�����iAmurrû�j�ƌĂ�A�����ŃC�X���G���̃J�i���蒅�ȑO�̐�Z�����̈�Ƃ��Č��y�����A�����l�ièmorî�j�Ɠ��肳�ꂽ�B�������E�n���Ƃ��Ẵ}���g�D/�A�����́A���\�|�^�~�A�̕����ɂ����āA�V�������l��A�b�J�h�l�Ƌ�ʂ����O���̐l�X���w���Ă���A�O�q�̑O2600�N���̃t�@���������ł̌��y�����o�ł���B�܂��A�}���g�D�̓��\�|�^�~�A���猩�Đ��̕��p���w����Ƃ��Ă��p����ꂽ���A���̌�`�ł́A�A�b�J�h�����̂R�Ԗڂ̉��}�j�V���g�D�V���i�O2269�]2255�N�j�̃I�x���X�N�Ɍ��y�����u���̕��m�������n�itu15
mar-tu�j�v���ł��Â��B���̂��Ƃ́A�����炭�A�}���g�D/�A�������{�����\�|�^�~�A�̐��Ɉʒu����n���ł���A�������̒n�Ƃ���l�X���}���g�D�l/�A�����l�ƌĂꂽ���Ƃ�����������̂ł��낤�B
�@�}���g�D/�A���������̒n���ƌ��т���f�[�^�������c���Ă���B�O2300�N���̃G�u�������́A�}���g�D�imar-tu.KI�j�����[�t���e�X�쉈���̃G�}���ƃo���t��͌��n��̃g�D�g�D���ɊW�Â���B�܂��A�A�b�J�h������S��̃i�����E�V���̓��[�t���e�X����u�}���g�D�̎R�ł���o�T���R�iBa-sa-ar
SA-DU3-i3 MAR.TU.KI�j�v�ɒB���A�����Ő�������Ƃ��L�^����B�����Ɍ��y�����o�T���R�́A�p���~���̖k���Ɉʒu���錻�݂̃r�V�����R���w���Ă���ƍl������B�i�����E�V���̌�p�҂ł���V�����E�J���E�V�������܂��N���u�V�����E�J���E�V�������o�T���R�ɂ����ă}���g�D��ł��j�����N�iin
MU sar-ka3-li2-LUGAL-ri2 MAR.TU-am in ba-sa-ar.
KUR is11-aru�j�v�ɂ����ă}���g�D�ƃr�V�����R�����ѕt���Ă���B���̉����̖ړI�͕K���������炩�łȂ����A���\�|�^�~�A�̔_�k�n�ɐi������V�q���ɑ��钦�������ł������\���������B�A�b�J�h����̒���ɂ����郉�K�V���̎x�z�҃O�f�A�̔蕶�iStatue
B�j�ɂ����āA�O�f�A�͐_�a���݂ɍۂ��āu�}���g�D�̎R�ł���r�V�����i�o�T���j�R�iba11-sal-la
hur-sag Mar-tu-ta�j�v�Ȃ�тɁu�}���g�D�̎R�ł���e�B�_�k�R�iti-da-num2
hur-sag mar-tu-ta�j�v����ނ��^�э����Ƃ��ւ��Ă���B�r�V�����R���}���g�D/�A�����l�̎R�Ƃ���`���͂���Ɍ��ɂ������p���ꂽ�B�V�A�b�V���A����̎ʖ{�������m���Ă���lipsur
litanies �Ƃ���F�����ɂ́A�r�V�����i�o�V�����j�R�iKUR
Ba-sar2�j���A�����̒n�̎R�iKUR A-mur-ri-i�j�Ƃ��Č��y�����B�܂��A�e�B�O���g�E�s���Z���P���i�O1114�|1076�N�j�̔N��L�̓r�V�����i�׃V�����j�R�iKUR
be2-es-ri�j�̂ӂ��Ƃ̗V�q�A�����l�iAhlamu-Aram�j�̂U�́u���X�v�i���W���H�j�̔j����L�^���Ă���A������Z���n�V�q���ƃr�V�����n������т���L�^�Ƃ��ċ����[���B
�@���\�|�^�~�A�ɂ�����}���g�D�ɘb��߂��ƁA�A�b�J�h��������ɂ́A�}���g�D�ƌĂ��O���̈ڏZ�҂ɂ��Ă̌��y�����K�V���A�E���}�A�A�_�u�A�X�T�Ȃǃ��\�|�^�~�A�Ƃ��̎��ӂő�������B�A�b�J�h��������̕����Ɍ����銯�E��ugula
mar-tu�����nu-banda3 mar-tu-ne�́A�}���g�D�l�����̑������邢�͎w�������Ӗ����A�ނ炪�����̓s�s�s�����ň��̌R���I������S���Ă������Ƃ��������킹��B
�@�E����3��������i�O2112�|2004�N�j�ɓ����ă}���g�D�ɂ��Ẵf�[�^�͂���ɑ�����B���ɃE����3�����̉ƒ{�ł̏W�ϒn�ł������v�Y���V���E�_�K������̕����ɂ́A�ƒ{�i�q�c�W�A���M�j�̒҂Ƃ��ă}���g�D�ɂ��Ă̑����̌��y��������B�C�V���A�����T�A�E���}�Ȃǂɂ��J���҂Ƃ��Ĕz������}���g�D�ɂ��Ă̌��y������B���̎���A���Ƀ��\�|�^�~�A�암�ɂ����āA�}���g�D�̈ꕔ�͂��łɓs�s�Z���Ƃ��Ē蒅���s�s�����ɓ������Ă����悤�Ɍ�����B����A�������烁�\�|�^�~�A�ւ̃}���g�D�̗����͌p�����Ă���A�E����3��������㔼�ɂ����āA�E���̍L��x�z���������N���҂��Ẵ}���g�D�͖����ł��Ȃ����݂ƂȂ�A�ނ�ɑ��鉓����A�ނ�̐N����h����nj��݂���Ă�ꂽ���Ƃ͂悭�m���Ă���B�V��������ŏ����ꂽ�_�b�u�}���g�D�̌����v�̃}���g�D�_�ɑ����ꂽ�s�т̒n�ɏZ�ޖ�ؐl�Ƃ��Ẵ}���g�D�̃C���[�W�́A���\�|�^�~�A�̖{���̓s�s�Z�����猩���}���g�D�ςf������̂ł��낤�B�����A�}���g�D�����\�|�^�~�A�����̔ނ�̌̒n�ɂ����Ăǂ̂悤�ȃ��C�t�E�X�^�C���Ő������Ă����������\�|�^�~�A�ɗR�����镶�w�e�N�X�g�Ɉˋ����Ĕ��f����킯�ɂ͂����܂��B����͑�����������̂́A�Ão�r���j�A����̃}�������́A�����̃A�����l�̐����`�Ԃ����[�t���e�X������ł̒�Z����b�Ƃ��锼�_�E���q�{�ł���A�q�r�҂Ƃ��Ă͒Z�����ړ��^�ł��������Ƃ���������B���������A�����l�ƃ��\�|�^�~�A�ɑ勓���ĎE�������A�����l�̃��C�t�E�X�^�C����̂��̂Ƃ��đ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@�Ƃ�����A�Ão�r���j�A����i�O2��N�I�O���j�ɂ́A�A������̐l�����������l�������T�A�o�r�����A�}���h�A�E���N�A�V�b�p���A�L�V���A�}���Ȃǂ̃��\�|�^�~�A�̎�v�s�s�̎x�z�҂Ƃ��Č����B�����āA�A�����l�����\�|�^�~�A�̎�v�Ȑl���\���v�f�ɂȂ�ɂ�āA�l���}���g�D/�A�����Ƃ��Ă킴�킴�w�����銵�s�͂������Ɏ���ꂽ�B�A�����l�̏������́A�}�������ȂǂɌ���悤�ɁA��菬���ȃT�u�E�O���[�v���\���镔�����i�Ⴆ�n�i�l�A�r�j���~�i�l�Ȃǁj�ɂ���ČĂ��悤�ɂȂ����B�Ão�r���j�A�������Ɏ���ƁA�A������̐l�����������l�𑽂�����郁�\�|�^�~�A�ɂ����āA�����I�ď̂Ƃ��ẴA�����Ƃ�����͂��܂�g�p����Ȃ��Ȃ����A�V���A��̂��邢�͂��̈ꕔ�̒n�悪�u�A�����̒n�v�ƌĂ��悤�ɂȂ��Ă������B
| �O3�|2��N�I�̃Z���l�ƃZ����Ɋւ���čl |
�@
��q�����Ƃ���A�A�����l�͑O�R��N�I���ɂ̓��\�|�^�~�A�ɂ����B���̎����ɉ����A�ߔN�̃G�u���A�}���A�e���E�x�C�_���ɂ�����O�R��N�I�̌ÃZ���ꕶ���̔����ɂ���āA�O2000�N���ɃA�����n�V�q�����V���A����������ӊe�n�ɑ�ړ����Ċg�U�����Ƃ��邩�čL��������Ă��������͌������𔗂��Ă����B�����ŁA���N�V���A�e�n�Ŕ��@�������s���A�����l�Ɋւ�镶�����������哱���Ă���G.
�u�b�`�F���e�B����Ă��鉼���iBuccellati 1992�j�Ɍ��y���Ė{�e�����т����B
�@�u�b�`�F���e�B�́A�A�����l�͖{���O2��N�I�̃}�������Ɍ�����悤�ȃ��[�t���e�X������̔��_�E���q�{�̑����Z���ł������Ƃ��A�ȉ��̂悤�ɐ��@����F����瑺���������͐쉈���Ɍ��肳�ꂽ�_�n���k�삷�����A�L��ȃX�e�b�v�n��ɖq�{�ɂ��o�ϊ����̊g�����āA�����炭���łɑO3��N�I����}���̓s�s�̌��͂ƓƓ��̊W��ۂ��Ă����B���������Z�������̈ꕔ�̓X�e�b�v�̉����܂Ői�o���ēs�s�̎x�z���痣�E���A�����ӎ����������{�i�I�ɗV�q�������A���������ړ����Ċe�n�Ɋg�U�����B���̃p�^�[���͑������炠�������A���ꂪ�ł���K�͂ɋN�������̂��A�O3��N�I������2��N�I���߂ł������Ƃ����B
�@
�G�u�������̌������i�ނɂ�āA�G�u����͓����̗\�z�𗠂��Đ��Z����������Z����ł���ÃA�b�J�h��ɋ߂�����ł��邱�Ƃ����炩�ɂȂ����B����ɂ���ă��[�t���e�X���p�ȕ��̐����𐼃Z���ꌗ�A�����𓌃Z���ꌗ�Ƃ���]���̌����͔j�]�����B����Ɋ֘A���āA����Œm���Ă���Z���n����̗��j�I���z���u�b�`�F���e�B�͎��̂悤�ɐ�������F
�@�O3��N�I�ɂ����āA�A������̓��[�t���e�X������Ƃ��̎��ӂ̑�������Ƃ��āA�A�b�J�h��̓��\�|�^�~�A�E�V���A�̏��s�s�ɗ��z�����s�s����Ƃ��āA�Δ�I�ɑ�������B
�A���҂͖{���L���Ӗ��ŋ��ʂ̓���������������i�Ök�Z����mEarly
North Semitic�n�j���������A�ێ�I�ŕω����ɂ�����������A������̕����{���̌���I������ۂ��A�A�b�J�h��͎���ƂƂ��ɋ}���ɕω����Ă������B
�B���҂͂������Ɍ���Ƃ��Ă̊u�����傫�����Ă����A�O2��N�I�㔼�ɂ̓��[�t���e�X������̑��������U�������ʐ��֗��������A�����n�Z�������Z����O���[�v�i�A������A�t�F�j�L�A��A�J�i���ꓙ�j�̑c�ƂȂ��āA���Z����Ɠ��Z����i�A�b�J�h��j�Ƃ̒n���I���ݕ��������������B
�@�u�b�`�F���e�B�̉����́A�O3��N�I������O2��N���O���̃V���A�E���\�|�^�~�A�̕����j���Ɍ���A�����l�ƃZ���n����Ɋւ���f�[�^���_�C�i�~�b�N�ɐ������Ă���A����̌����̂�������ƂȂ���̂Ƃ�����B�A�����l�̒n�Ƃ��ČÂ��`�����c��r�V�����R�Ƃ��̎��Ӓn�����
����V���Ȓ��������̐��ʂ��A���������p���_�C���ƑΏƂ����͂����ׂ��ł��낤�B
�i2006�N1��28���@�L�j
�@���M�ɂ�����A�O��a��搶�ɑ��e���������������A�M�d�Ȃ��w�E���������������ƂŁA�������̌�T��Ƃ�邱�Ƃ��ł����B�L���Ă���\���グ�����B�Ȃ��{�e�Ɏc����_�ɂ��ẮA�����܂ł��Ȃ��S�ʓI�ɕM�҂̐ӔC�ł���B
Ambar, M. 1991: Les tribus amurrites de Mari, Orbis Biblicus et
Orientalis 108, Göttingen.
Buccellati, G. 1966: The Amorites of the Ur III Period, Napoli.
Buccellati, G. 1992: �gEbla and the Amorites,�hin C.H. Gordon and
G.A. Rendsburg (eds.), Eblatica: Essays
on the Ebla Archives and Eblaite Language, vol. 3, Winona Lake,
Indiana, 83-104.
Catagnoti, A. 1998: �gThe III Millennium Personal Names from the
Habur Triangle in the Ebla, Brak and
Mozan Texts,�hSUBARTU, IV/2, Turnhout, 41-66.
Edzard, D.O. 1989: �gMartu,�hReallexikon der Assyriologie, Band 7,
433-440.
Hitti, P.K., 1937: History of the Arabs, London.
Kupper, J.-R. 1957: Les nomades en Mésopotamie au temps des rois
de Mari, Paris.
Lerberghe, K. van 1996:�gThe Beydar Tablets and the History of the
Northern Jazirah,�hSUBARTU, II,
Turnhout, 119-122.
Liverani, M. 1973: �gThe Amorites,�hin D.J. Wiseman (ed.), People
of Old Testament Times, Oxford, 100-
133.
Streck, M.P. 2000: Das amurritische Onomastikon der albabylonischen
Zeit, Band 1: Die Amurriter: Die
onomastische Forschung, Orthographie und Phonologie, Nominal morphologie,
AOAT 271/1,
Münster.
Whiting, R.H. 1995: �gAmorite Tribes and Nations of Second Millennium
Western Asia,�hin J. Sasson (ed.),
Civilizations of the Ancient Near East, vol. II, New York, 1231-1242.
Wilcke, C. 1969: �gZur Geschichite der Amorriter in der Ur III Zeit,�hWO 5, 1-31. |
 |
|
| �@ |
|
 |
| |
| Copyright (C) 2005-2007 Kokushikan University |
|
|