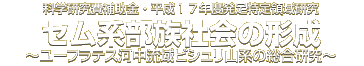この研究の契機は、本研究代表者らが1970年代に手を初めたテル・グッバの発掘とその遺構復原の研究にさかのぼる(図1)。場所はメソポタミア北東部、イラクのディヤラ川流域にあるハムリン盆地。発掘された遺構は全7層にわたるが、研究課題はもっぱら最下層の全面に広く展開する同心円状の稀有な建物だった。
ジェムデト・ナスル期(前3000年頃)を通じて存続したという年代観が与えられている(注1)。建物全体は長径約80mの卵形平面をなすが、ほぼ完全に掘りあげられた中心部分を観察すると、中心から第4番目と数える壁体までは、平面上完全な幾何学円に則って日乾煉瓦が積まれていることが判明した。これら中心部の煉瓦積みと、その外側を囲む第5の壁は、床からの高さ4m近くまで遺存していた。残念ながらこの遺跡は人工湖に水没する定めになっていたためもはや現存しないが、発掘完了時の遺構は40分の1の模型としてその形状は残されている。 |

図1 テル・グッバ第7層発掘の円形遺構中心部(1979年) |
| この建物がもとはどんな目的で築かれたのか、どういう形態を有していたのか、考古や建築の専門家たちの議論が白熱した。機能面からの考察にあたっては、神殿か、倉庫か、要塞か、あるいはその組み合わせや歴史的変化など様々な仮説が出されたまま今日に至っている。一方、形の復原という課題については、おおよその共通認識を得ることができた。発掘遺構の模型が、というより模型製作のプロセスが、その上部の復原形状を考える際に大いに役立った(注2)。正確に円の軌跡を描く平面形、放射状に積まれた日乾煉瓦の壁体、持ち送りの擬似ヴォールトを見せる開口や通路、第4の壁上端の傾き等々、上部構造にドームを想定する見解に異論はなかった(図2)。工法として、個々の煉瓦を若干内向きに傾かせた迫持ち状態のリングを重ねる組積法であり、その施工手順から、正三角形を内接させるという尖頭形のドーム形状が想定された。それは、当時すでに、煉瓦積みの技術に熟達した人たちがいたことを物語る。現在も東イランや中央アジアで実例を見ることのできる構造である。ほかにも比較参照の対象は、ハラフ期のトロス建築や、ミケナイ文化のトロス墓、北シリアにいまも見られる「蜂の巣型」住居、その起源を思わせるキプロスや北イランの円形家屋の集落遺跡、さらにはイランのチャハル・タークやイスラームのドームにまで及んだ。 |
さらに、この遺構と規範を同じくする類例は、メソポタミア低地部には全く見られないにもかかわらず、グッバのほかハムリン盆地に若干と、西に隣接するアダイム川流域の盆地にも分布することが知られる(注3)。
テル・グッバの建築を実現した工人たちは、シュメール、バビロニアといった文明の中枢を担った人々とは、異なった建築伝統を育んでいたにちがいない。
グッバの復原研究以後、西アジア地域で数多くの歴史的遺構と接するなかで、石積み、煉瓦積みの多様さ、巧みさを私たちは見いだしてきたが、そのたびに、筆者はテル・グッバの卓越した遺構を思い返すのである。 |

図2 テル・グッバ円形遺構の復原模型
(1980年) |
古代西アジアの建築組積を追求しようとする本研究は、比較の観点からできるだけ広域に事例を求める必要を実感している。ユーフラテス中流域の遺構事例の調査は無論必要だが、準備の関係上2005年度は、同じセム系の民族が文明の足跡を残すレバノン国内の遺跡を対象とし、建築遺構にみる組積造の特徴を調査した。訪れて観察した遺跡を旅程順に振り返ると以下の通り。 |
- ベイルート市中、中世教会と古いモスクを中心にフェニキア時代やローマ時代の遺構。
- ベイト・メリ修道院周辺のローマ時代神殿の痕跡。
- ベカー盆地のニハに建つ2棟のローマ期神殿。
- バールベクにあるユピテル、バッカス、ヴェヌスのローマ時代3神殿。
- アンジャールの初期イスラーム都市遺跡とマジダル・アンジャルの神殿。
- ティールのローマ時代からビザンティン時代の都市遺跡とラマリ地区墳墓群。
- ティール郊外のティブニン城。
- ティールの水源ラスル・アイン。
- シドンの旧市街と中世城郭。
- エシュムーン遺跡に見る前1千年紀(新バビロニア時代)の城壁、およびビザンティン時代遺構。
- シュヒム遺跡の主としてビザンティン時代の教会と搾油施設。
- ビブロス遺跡の青銅器時代遺構の多様な城壁と、ビザンティン時代教会および城郭。
これらの遺跡に見出される多様な建築組積に注目すると、いきおいローマ時代に著しく進歩し広く普及した石積みに観察の目が偏りがちだが、それ以前の時代にも風土や伝統技術を反映したと見られる興味深い遺構がある。その典型例として、レバノンの南40km余に位置するエシュムーン遺跡をまず取り上げたい。
|
ローマ、ビザンティンのモザイク床の華麗さでも名高い遺跡だが、もとは遺跡と同名の神に捧げられたフェニキア人の聖地である。
ここでは複雑に折り重なる石の壁に注目したい。時代によってこれほど極端に石積みの技法を変化させる遺跡は、めったに出会えるものではなく、観察する私たちに遺跡を訪ねる楽しさ十分に味わわせてくれる。一見してわかる石工技術の多様さがビブロス遺跡と共通する点と、古くはアケメネス朝ペルシアの時代以前にまで遡ると説明される考古学上の編年観は、西アジアにおけるレバノン固有の、まちがいなくフェニキア人の活躍した領域としての地域性を強く印象づける。
なかでも「新バビロニア時代」と年代付けられる基壇の残滓である勾配つきの壁体は、ここでは特異であると同時に、遺跡中でも最も古い時期の組積とされる。その20度前後の勾配と磨いたような仕上げの切石積は、より東方のセム系世界よりも、エジプトの伝統技術を想起させる(図3)。まったく同様な組積が、ビブロスの「ペルシア時代の城塞」の北東側にも遺存する。
その由来を含め、工人集団の移動、消長を反映するものとして、より注意深い考察を進める必要があるだろう。 |

図3 エシュムーン、新バビロニア時代とされる傾斜組積(2006年)
|
ペルシア帝国が伸張した時代、エシュムーンには切石積みの壮大な基壇が南側の丘に沿って営まれる。その石材の大きさと、額縁状の表面仕上げが時代を物語る(図4)。
その足元に設けられた「アシュタルテの玉座」を擁する聖域の囲壁はヘレニズム時代を代表し、その組積は石材の小口を縦置きにして並べるという特徴を持つ(図5)。
上方の斜面に沿って長く延びる城壁にも同様の手法がみられる。
城壁の組積における石材のこうした扱いは、ギリシアのメッセネ遺跡やヨルダンのウム・カイス遺跡にも見られ、東地中海世界のヘレニズム期に通有の組積だった可能性がある。このように、エシュムーンは、地域の特性が薄められるローマ時代以前の組積造を知ることのできるレバノンでは数少ない時代の遺跡なのである。調査記録を精査する必要を痛感しているが、まだその作業は緒についたところである。
ローマ時代の遺構の中では、やはりバールベクに見るべきものが多い。巨石の使用や石の彫刻に目を見張るのはもちろんだが、建築史的には、ユピテル神殿の大中庭に面するエクセドラの上部に架かる曲版の巧みさをまず特筆したい。8分の5円の平面形に載るドーム曲面を、正8角形を描く直線で分割するという、合理性や必然とはかけ離れた解決法で石材を組む(図6)。
同じ遺跡に建つヴェヌスの神殿の上部架構も同様だが、こちらはドームを同心円で切り取っていたと推定される(図7)。
これらは、西アジア地域における切石を組み上げた曲板の事例として最高の技術水準を示すといえるが、石工の技術をさらに進め、正方形平面の空間に切石ドームを架けるという事例がヨルダンを中心に散見される。ジェラシュの西浴場付属棟やウム・カイスの地下墓廟などが該当する(注4)。
いずれの遺構も、紀元2世紀後半を前後する時代とするのが通説であり、円熟した技術に裏打ちされてその時期に流行した石造ファッションと言えるのかもしれない。南レバノンのティールにのこるローマないしビザンティン時代の墓所にも、かすかな痕跡ながら、扁平な曲面を切石で組んだ遺構が現存する(図8)。
これらについてはヨルダンの調査報告として、いずれ稿を改めて考察したい。
矩形平面にドームを架ける組積構法については、クレスウェルがペンデンティヴ・ドームとの関係ですでに注目しており、建築史におけるペンデンティヴ成立の重要性を早くに指摘している(注5)。彼は地中海からオリエントにかけての広い地域を視野に入れつつ、エジプトやアッシリアの事例にまで遡り、その到達点は、6世紀、イスタンブルのハギア・ソフィアとみる。その過程において、古来各地でドームを架けるために擬似的ないし初歩的ペンデンティヴの採用が試みられたが、原理的な意味で完成した事例を確認できるのは、シリア、パレスティナ地方、2世紀後半のはじめ頃だったようである。
ほかにも多くの建築史家が、ドームの系譜について業績を残しているが、正面から『四角形に載るドーム』を書名としたJ.フィンクによる研究では、「東方世界において方形の上に円蓋を据えるという課題にとって、西方から利益を得ようとしても無駄である」「技術上の発明として、方形の上に載る円蓋はまったく東方のもの」「小アジアと結び付けて考えるべきで、円蓋形状の発祥地は小アジアとみる」という認識であり、まだまだ検証する余地が残されている(注6)。
ここでは紀元前後の時代からヨルダンを含むレバント地域に限って初期イスラームの時代にまで継承されるという可能性を指摘しておきたい。
以上は今回の調査成果のごく一端だが、このたび訪ねたレバノンの遺跡をふり返ると、ビブロスを除いて先史期の遺跡が乏しく、当地域に石造以外の建築、とくに日乾煉瓦建築の伝統がどの程度まで浸透していたのか見きわめることができなかった。今後の課題としたい。
なお、初期イスラームの都市アンジャールの遺跡について、今回の調査に基づく研究分担者の意欲的な復元的考察の一端が公表されている(注7)。
|

図4 エシュムーン、アケメネス朝ペルシア時代とされる巨石積みの擁壁(2006年) |

図5 エシュムーン、アシュタルテの聖所の石造壁(2006年) |

図6 バールベク、ユピテル神殿中庭エクセドラの架構(2005年) |

図7 バールベク、ヴェヌスの神殿、上部架構の痕跡(2005年) |

図8 ティール、ゴルフ・マトワニーヤ、切石組による天井架構(2006年) |
|
|
今回の調査を通じ、この特定領域研究における建築組積技術の一つの焦点として、ドーム架構ないしはそれに準じた曲板の組積術に、私たちはますます注目するようになった。その到達点でありかつその後のドーム建築の規範とされるハギア・ソフィアのペンデンティヴ型ドームに至る技術系譜は必ずしも明らかではなく、それを遡る時代について広域に事例を検証する必要がある。
とくにかつてローマ領であったシリア、レバントというセム系民族の土地に遺された建築遺構は重要である。同じ時代、イタリア半島ですでに普及していたコンクリート工法が、当地方にはなぜか普及せず、彼らは切り石組積にこだわった。そうした観点から、レバノンに続いて今夏はヨルダン領内の遺構を重点的に観察した。近々報告する予定である。
またレバノンでは全く接することのできなかったアドベ(日乾煉瓦)の遺構をはじめ、上部構造以外の建築組積についても、今後は注意を払いたい。石造や焼成煉瓦造の遺構に比べ、アドベ遺構の検証は難しい。現在の知見では、ヴォールト架構については、メソポタミアとエジプトで早い時期(前3千年紀末頃)に発達したことがわかっているものの、イラン、アナトリアにアドベによる曲板架構の例はきわめて乏しい。ビシュリ山系における今後の考古学的調査は、果たしてどのような事例をもたらしてくれるだろうか。新たな資料と知見が得られることを大いに期待している。 |
1)詳しくは『ラーフィダーン』第2巻(1981)所収の特集記事「イラク・ハムリン発掘調査概報」。
2)この復原研究については、科研特定研究の報告『イラク、テル・グッバ第Ⅶ層発掘の建築遺構復原に関する研究』(1982)。
3)『ラーフィダーン』第11巻(1990)所収、藤井秀夫・井博幸「アル・アダイム地域の予備調査」による。
4)ウム・カイスの事例は、T. -M. Weber Gadara - Umm Qes , I (Harrassowitz, Wiesbaden 2002)に報告があり、拙稿「ガダラのドーミカル・ヴォールトA domical vault at Gadara, Jordan」(『第12回ヘレニズム~イスラーム考古学研究』(2005)所収)でもその重要性を論じた。
5)Cresswell, K.A.C. Early Muslim Architecture I, Umayyads, Early 'Abbasids & Tulunids(Oxford, 1932).
6)Fink, Josef Die Kuppel über dem Viereck, Ursprung und Gestalt (Freiburg/Munchen,
1958).
7)第30回地中海学会大会で、本計画研究の研究分担者、深見奈緒子氏が「アンジャール―初期イスラームの宮殿都市への考察」と題して発表した。 |