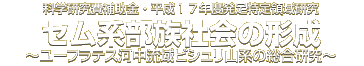|
|
 |
 |
 |
| ■ 本研究の趣旨 ■ |
| 編年表でいうと |
 |
このことを、別の角度から説明してみましょう。
ここに4つの遺跡の編年表があります。
従来の考古学では、都市と周辺小遺跡との関係性を具体的に捉えることはありませんでした。
というのも、大型都市遺跡だけに力点が置かれ、その周囲の小型遺跡にまでは手が及ばなかったからです。
本研究では、この両者を一つのシステムとして、一体的に調査・研究します。
従って、例えば都市遺跡Bと、周辺の小型農村との比較から、周辺の農民が都市社会に編入される過程であるとか、逆に、都市から離脱して別の集落を形成する過程であるとか、再度、都市に組み込まれる過程、などの動態が、追跡可能になります。
遺跡Cについても、同じことが言えます。
小さなキャンプを営んでいた遊牧集団が、都市の一部に入り込んだり、そこから離脱して別のキャンプを開設したりする、その生きた過程を跡づけることができるわけです。
こうした矢印付きの、生きた編年表を作成すること、つまり、部族性をキーワードに、中東都市の歴史的・構造的な生態を明らかにすること、それが本研究のねらいなのです。 |
 |
|
| |
|
 |
| |
| Copyright (C) 2005-2007 Kokushikan University |
|
|